キッチンの整理収納を徹底解説!場所別アイデアとコツ
ideas
10min










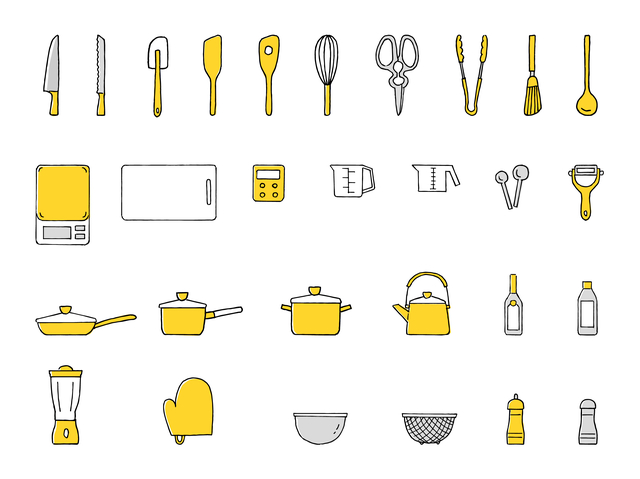





























吊戸棚
シンク下
調理台下
コンロ下
冷蔵庫
周辺収納(食器、家電)